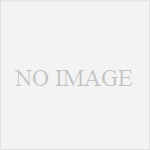※25.9.12下の方に追記しました。
医療データ利活用について思うこと。利活用と保護を両立する制度自体はちゃんとあるが、その制度があまりワークしていないように見える。個人情報保護観点で見たときにホワイトデータが優遇されずに、グレーデータ・ブラックデータも流通しているようにも見える(印象論だが)。
実態として、どのような利活用ニーズがあって、現状の制度の具体的にどの部分が障壁になっているのか。それを知ることができれば、制度改善の提言など、いくらでもできると私としては思っている。
実態を知る機会というのが、お知り合いからコツコツ教えていただくといった場面しかなかったものの、医薬産業政策研究所のレポートが公表されていると知り、読んでみました。このようなレポートを私は欲していたのです!ありがたや!
2025年07月ポジションペーパー「公的データベース等の利活用に関する製薬企業調査報告」
https://www.jpma.or.jp/opir/positionpaper/pp_007/tpdsn80000000clo-att/pp_007.pdf
https://www.jpma.or.jp/opir/positionpaper/pp_007/article_007.html
https://www.jpma.or.jp/opir/u15at700000002sf-att/News-75_03.pdf
https://www.jpma.or.jp/opir/u15at700000002sf-att/News-75_04.pdf
以下、へーと思った点。
- 公的DB等:公的DB+次世代医療基盤法DB
- 臨床検査値、画像データ、医師所見、任意接種記録を望む声が多かったとのこと
- 疾患領域は抗悪性腫瘍剤が最多。次にその他。次が全身性抗感染症薬(P23)
- 外資系企業の方が公的DB等活用検討割合が高い
- 商用データ並みの使いやすさを求める声も。
- 公的DB等の欠点
- 審査・承認手続が煩雑で、制度の柔軟性が低い(商用データの方が良い)。
- スピード感にかける(1年以上かかることもある)(商用データの方が良い)。
3か月以内の提供を求める声多し(32P→https://www.jpma.or.jp/opir/u15at700000002sf-att/News-75_03.pdf)。 - 解析に専門リソースや外部支援が必要で総コストが高くなる(商用データの方が良い)
- 分析スキルを外部に依存することになるので社内スキルが蓄積されない
- アウトカム情報や死亡情報の欠如・非構造化
- 患者背景情報(社会経済状況や日常生活情報など)やカルテ由来情報(医師所見、治療効果、治療中断理由等)、臨床検査値や画像・病理情報、バイオマーカーなどの検査情報が不足(34P→https://www.jpma.or.jp/opir/u15at700000002sf-att/News-75_03.pdf)。
- コストは明確化が重要で、金額はPJによるらしい。1利用あたりの許容可能な利用料に関する自由記述では、100万円未満から3,000万円超まで幅広い見解が寄せられた(32P→https://www.jpma.or.jp/opir/u15at700000002sf-att/News-75_03.pdf)。
- 公的DBへの期待
- 網羅性・悉皆性
- 患者単位での追跡
- 介護、予防接種、自治体健診情報などは商用データにない
以下、水町感想。
- 商用データは、簡単に早く使えて、コストがわかりやすい模様。ここが民間と役所等の違いか。まあ、一般論からしても、それが民営化の理由だわな。データだけあってもしょうがなくて、解析ツールとかも必要だし、データ入手のための手続・コストの明確化が必要、と。
- 顕名データに戻すというニーズはないのか?
- 商用データになく、公的DBにもない情報(例、カルテDBに含まれない検査情報・医師所見・患者背景情報、死亡情報含むアウトカムなど)や、各種情報の連結を、次世代医療基盤法で行うと良いのか?カルテDBに含まれない生カルテ情報と、死亡情報などのアウトカム情報をできる限り網羅的に入れて、あとは他データとの連結があれば、よい?
- 薬事承認など、公益性が高くニーズも高くインパクトも大きい分野で利活用できるよう、複数データホルダー・データ整備者・製薬企業・PMDAなどを巻き込んだ(机上)実証実験などを行っては? 結局、信頼性や品質、データ欠損、データ量の問題など、いろいろあって、薬事にどれだけ使えるか不明であり、その問題点の洗い出しが必要かも。
- いまさらだが、認定事業者自らがデータを収集してきて、そこで競うという建付けではなく、データをどう使いやすく整備するかを民間が競うという建付けが良かったのかも。
でもそうするとデータは公的機関にいったん集約して、そのデータを解析するツールや解析する技術を民間が競うとなりがち。ただ、それだと、公的機関が全医療データを集中して保持することのリスクもあり、ここを国直営にはしづらいような。
となると、やっぱり今の建付けで、データホルダーに提供義務、そして提供インセンティブを付与して、認定事業者がデータを収集するところで競う形にはせずに、データを連結したり解析したりの、使いやすさで競うということになるか。 - 25.9.12追記。提供義務といっても、さすがに、全データホルダーに提供義務をかけるというのはナンセンス。利活用サイドもさすがに全データホルダーに提供義務をかけるべきという意向ではないように思ったけど、違うのかな。加藤先生の非常に詳しいご発表でも、EHDSで、従業員10人未満かつ年間売上高または貸借対照表が200万ユーロ未満の企業は二次利用の提供義務等の例外とあったし。そりゃ、全データホルダーに網羅的な提供義務というのはいくらなんでも無理でしょう。例えるなら、会社で受けたお問合せ記録すべてに提供義務かけるとか無理だし、弁護士がクライアントに提出した全メモを全部DBに集める提供義務かけるとかも難しいでしょうし。
参考:https://nk.jiho.jp/article/201760 - 25.9.12追記。EHDSについて、内閣府検討会第1回の事務局資料と、第2回の加藤先生ご発表資料、くわしくてわかりやすい。第1回事務局提出資料は、EHDSに限らず、厚労省の取組、次世代医療基盤法の現状、個人情報保護法改正状況も、最新取組・状況がわかりやすくまとまっていて、読みやすい。