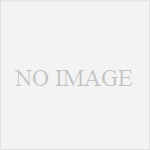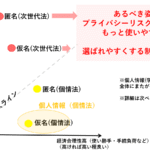カーネギー「人を動かす」でお勧めされていたので、図書館で世界の名著を借りてきて、「フランクリン自伝」を読んでみました。渡辺利雄訳。この本では、フランクリン自伝の前半に当たる全体のおおよそ1/2と、最後の部分およそ1/10だそう。なぜ略されているのかよくわからないけれども、最初にそのような注記があった。
はじめは、なんか読みにくい文章だなと思ったけれども、すごいな、と。
覚えておきたい点と感想。
- ソクラテスメソッドでのソクラテスは謙遜な態度で物を尋ね、どうも自分は納得がいかないのだがといった様子で尋ねる。
- フランクリンは次のように話すことにした。「私はこんな風に理解しています」「私にはこう思われます」「たぶんそうかと思います」「私が間違っていなければ、こういうことでしょう」
- フランクリンは、図書館構想を思いついて、賛同を求めて個別訪問などをしたが、自分の発案だというと協力が得られないので、友人たちの発案で私はただ個別訪問に回っているだけみたいに言うと、他の人の協力が得られやすかった。
- フランクリンのころは、経済的に恵まれていなくても、明晰な子ども・若者を評価する気風があって、お金持ちや年長者でそういう子ども・若者に目をかける人がいたりして、また社会全体がチャレンジ精神が合って、まったく知り合いがいないような環境に流れ着いてそこでも就職先を得られるなど、社会が硬直化していないというか受け入れられる環境があるように思って、それでフランクリンは成功したように最初は思った。でも、ゆっくり考えると、誰かに目をかけられて成功したというのではなく(逆に全く頼りにならない名士などが出てくる)、その時その時の場所で一生懸命やっていたら、成果を出すことができ、それが徐々に積みあがっていたということではないかと。ただ、いわゆる徳川家康とかのような本当にしんどい地獄のような苦労などは書かれていないので、日本の偉人伝によくある、苦労と達成みたいな感じではなく、着実に堅実に努力すると成果が積みあがる的な自伝のように思い、大河ドラマとかになるようなストーリーではないなと思った。