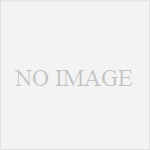今まで、マイナンバー最高裁判決について資料化したことがなかったので。
令和4年(オ)第39号 マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件 令和5年3月9日 第一小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/091846_hanrei.pdf
事案の概要:
- 憲法13条の保障するプライバシー権を違法に侵害するものであるから、プライバシー権に基づく妨害予防請求又は妨害排除請求として、個人番号の利用、提供等の差止め及び保存されている個人番号の削除を求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求めた事案。
判例要旨:
- 目的の正当性:
番号法は、個人番号等の有する対象者識別機能を活用して、行政運営の効率化、給付と負担の公正性の確保、国民の利便性向上を図ること等を目的とするものであり、正当な行政目的を有する。 - 理論上のリスクはある:
特定個人情報の中には、個人の所得や社会保障の受給歴等の秘匿性の高い情報が多数含まれることになるところ、理論上は、対象者識別機能を有する個人番号を利用してこれらの情報の集約や突合を行い、個人の分析をすることが可能であるため、具体的な法制度や実際に使用されるシステムの内容次第では、これらの情報が芋づる式に外部に流出することや、不当なデータマッチング、すなわち、行政機関等が番号利用法上許される範囲を超えて他の行政機関等から特定の個人に係る複数の特定個人情報の提供を受けるなどしてこれらを突合することにより、特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じ得る。 - リスク対策が講じられている:
しかし、利用・提供について厳格な規制を行い、安全管理措置を義務付け、規制の実効性を担保するため、悪質な違反行為には罰則を科し、法定刑を加重し、独立した第三者機関に種々の権限を付与している。分散管理を行い、情報提供ネットワークシステムには総務大臣の確認と情報提供等記録があり、本人開示も可能。閉域網で個人番号とは異なる符号を用いて情報連携がなされ、通信や情報自体も暗号化される。個人番号の変更も可能。そのため、法制度上又はシステム技術上の不備があり、そのために特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。 - 結論:
憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないと解するのが相当である。 - 裁判官:
裁判長裁判官 深山卓也 裁判官 山口 厚 裁判官 安浪亮介 裁判官 岡 正晶 裁判官 堺 徹
水町感想:住基ネット判決的な判決である。